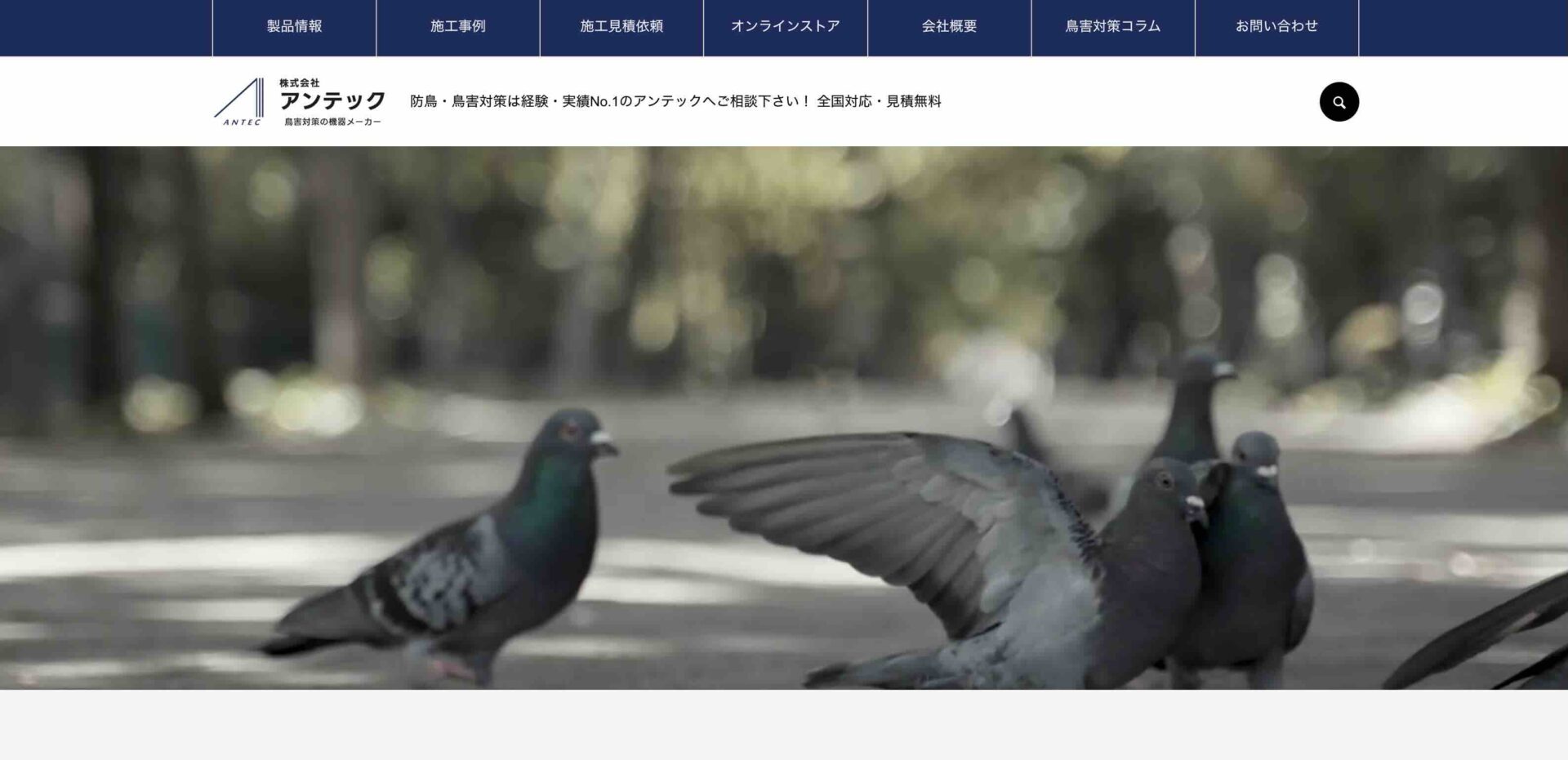近年、都市部を中心にムクドリによる騒音やフン害が深刻化しています。ムクドリの被害に頭を悩ませ、個人で解決したいと考えている人もいるでしょう。しかし、ムクドリは法律で保護されている鳥であるため、無許可での捕獲や殺傷はできません。そこで、今回はムクドリがもたらす具体的な害や解決策について解説します。
ムクドリの特徴
ムクドリは、比較的小型の鳥です。成鳥の体長は約24cm程度で、ハトより小さく、ヒヨドリに近いサイズ感を持っています。外見的な特徴としては、頭から背中にかけては濃い褐色、腹部は白っぽい色をしており、くちばしと足は橙色なのが特徴です。ムクドリは本来、森林や農耕地に生息し、農作物に被害をもたらす害虫を食べる益鳥としての側面も持っていました。
しかし、近年は都市化の進展に伴い、生息域を都市部へと変えてきているのです。ムクドリは社会性の高い鳥で、集団で生活し、集団で移動する習性があります。
彼らの鳴き声は「ギュルギュル」「ジャアジャア」「キュルキュル」といった、やや甲高いもので、大群が集合する際の鳴き声は、想像以上に大きいです。繁殖期は春から夏にかけてあり、ペアで行動し、民家の屋根裏や戸袋、換気扇の隙間など、雨風をしのげる場所に巣を作ることもあり、被害の原因となることがあります。
ムクドリの群れが形成される場所は、通常、交通量の多い道路沿いや、集合住宅の近くの大きな樹木など、人間活動が活発なエリアに集中する傾向があります。また、ムクドリは環境の変化に対する適応能力が高く、一度安全な場所と認識したねぐらは容易に変えないため、被害が定着しやすいという性質も持っているのです。
ムクドリがもたらす害とは
ムクドリの大群が特定の場所にねぐらを形成することで、住民生活や都市環境に悪影響をもたらすことがあります。おもな被害は、騒音やフン害、衛生的な問題の3つです。騒音
まず、ムクドリによる騒音は、被害のなかでも広範囲に影響を及ぼす問題です。とくに被害が集中するのは、夕方から夜間にかけての時間帯です。何千というムクドリがねぐらに集結し、一斉に鳴き交わすことで発生する騒音は、通常の生活音や交通騒音を凌駕することもあります。絶え間ない大音量の鳴き声は、ねぐらとなっている街路樹や電線直下の住民にとって、深刻な問題となってしまいます。
また、ムクドリは早朝から活動を始めるため、夜明け前の鳴き声も、住民の睡眠を妨げる要因となるでしょう。
フン害
次に挙げられる問題は、ムクドリのフンです。ムクドリが集団で休息する場所の直下は、大量のフンによって汚染されてしまいます。フン害は、景観を損なうという問題があり、商業施設や公共施設の入り口付近がフンまみれになると、利用者や通行人に不快感を与え、客足の減少につながりかねません。
さらに深刻なのは、フンによる物質的な被害と清掃コストです。フンには酸性の成分が含まれており、建物の外壁や屋根、設置された看板、駐車してある車の塗装などに付着すると、変色や劣化、腐食を引き起こす可能性があります。
また、フンが付着した場所の清掃には、洗剤や高圧洗浄機が必要となり、経済的な負担が増加してしまいます。また、建物の換気口やエアコンの室外機などにフンが溜まると、機器の故障や、異臭の原因となることもあり、修理費用や交換費用といった間接的な経済的損失も発生してしまうでしょう。
衛生問題
そして、ムクドリのフンは、公衆衛生上のリスクも伴います。鳥のフンには、人間に感染する可能性のある病原菌や真菌(カビ)、寄生虫などが含まれていることがあります。代表的なものとしては、クリプトコッカス症やオウム病(クラミジア症)などの人獣共通感染症です。とくに、危険なのは、フンが乾燥して粉末状になり、空気中に舞い上がって人が吸い込んでしまうケースです。
免疫力が低下している高齢者や、乳幼児、基礎疾患を持った人がフンから病原体を吸い込むと、重篤な呼吸器系の疾患や、全身の感染症を引き起こす可能性があります。
また、ムクドリの巣やねぐらには、ダニやノミといった吸血性の害虫が潜んでいることが多く、皮膚炎やアレルギーの原因となることもあるので、注意が必要です。
ムクドリを個人で撃退する方法
ムクドリによる騒音やフン害の被害を軽減するために、個人でできる対策や撃退方法をいくつか紹介します。ムクドリは「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(鳥獣保護管理法)によって許可なく捕獲・殺傷することが禁止されています。このことを考慮して、対策を行いましょう。個人でできる対策は、あくまでもムクドリを傷つけることなく、追い払う、あるいは侵入を物理的に防ぐ方法に限定されます。ムクドリがいる場所を「安全ではない」「居心地が悪い」と感じさせるための対策として、忌避剤(きひざい)を利用した追い払い策が挙げられます。
また、ムクドリは、天敵であるカラスやタカ、フクロウなどの猛禽類の鳴き声や、ムクドリ自身が危険を感じた際の警戒音を嫌います。そのため、天敵となる鳥の音声を録音したものをスピーカーで流すことで、ムクドリを威嚇し、追い払う効果が期待できるでしょう。
しかし、ムクドリは賢く、同じ音が繰り返し流されると、それが偽物であるとすぐに学習して、慣れてしまう傾向があります。したがって、対策の効果を持続させるためには、音源を不規則に変えたり、音量を調整したりすることに加え、音を流す時間帯を毎日変えるなどの工夫と、継続的な努力が必要です。
また、ムクドリは、不規則で強い光やきらめきを嫌います。自宅のベランダや軒先、庭木などに、CDやアルミホイル、または専用のホログラムテープや反射板を吊るすことで、太陽光を反射させてムクドリを警戒させる方法も有効です。
次に、ムクドリが物理的に止まれない、あるいは入ってこられないようにする対策もあります。ムクドリがとくに頻繁に止まる場所や、巣作りを試みるベランダ、軒先、窓のひさしなどに、目の細かい防鳥ネットを張ることで、物理的に侵入を防ぐことが可能です。
ネットの目が荒いと、ムクドリがネットをくぐり抜けたり、絡まってしまったりする可能性があるため、細かい目合いのネットを選ぶといいでしょう。一度設置すれば、長期間にわたって効果を発揮しますが、高所作業が必要となる場合や、広い範囲に設置する場合は、個人での作業が難しいので、注意が必要です。
また、手すりや室外機の天板、看板の縁など、ムクドリがよく止まる特定の場所には、バードスパイク(剣山)の設置が効果的です。ムクドリを傷つけることなく、物理的に止まれないようにするためのもので、比較的安価で設置も容易です。
個人でできる対策は多岐にわたりますが、ムクドリの学習能力の高さや、大群で行動するという特性から、根本的な対策が難しいことが多いのが実情です。被害の規模が大きい場合や、継続的な対策に疲弊してしまった場合は、専門家に頼ることをおすすめします。
被害が深刻な場合は専門業者に任せよう
個人でさまざまな対策を講じても、ムクドリの大群による被害がおさまらない場合は、専門の駆除業者に依頼することをおすすめします。専門業者は、ムクドリの生態や習性を熟知しており、個人では難しい広範囲かつ効果的な対策を実施できます。ムクドリ駆除における課題のひとつが、鳥獣保護管理法です。専門業者は法律を深く理解しており、法を遵守した形で、ムクドリを傷つけることなく、安全に追い払うためのノウハウを持っています。
捕獲許可が必要なケースや、巣の撤去が可能なタイミングなど、専門的な判断と手続きが必要な場面で、適切な対応をおこなってくれるでしょう。業者は、まず現地を詳細に調査・診断し、被害の根源(ねぐら、巣作り場所など)を特定します。
調査の上で、ムクドリが持つ学習能力に対抗するため、忌避音、光、物理的な防除(ネットやスパイク)といった複数の対策を組み合わせた、複合的なアプローチを提案し実行します。
専門業者を選ぶ際には、実績と信頼性をチェックしましょう。確かな実績と誠実な対応をおこなう業者に依頼することで、ムクドリの騒音やフン害から解放され、平穏な生活を取り戻せるでしょう。